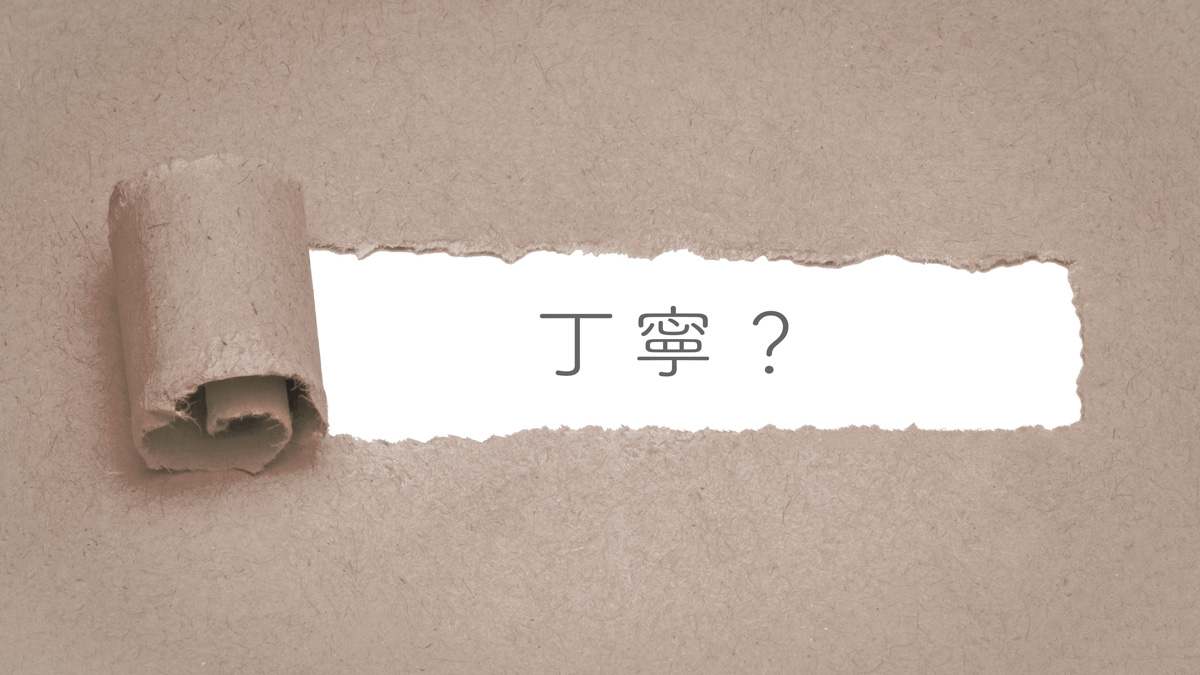
「丁寧な暮らし」「丁寧な生き方」「丁寧なものづくり」──
そんな言葉をよく耳にする。
「丁寧」という言葉は、たいてい何かを修飾するかたちで使われる。
そもそも、丁寧ってなんだろうか。
注意深い、細部にまでこだわった、几帳面な、気を配った、慎重な、入念な、などなど。
言葉は違っても、どれも「どんな心で向き合うか」という点で共通している。
つまるところ、丁寧とは、心の在り方や姿勢なのだと思う。
憧れとしての丁寧
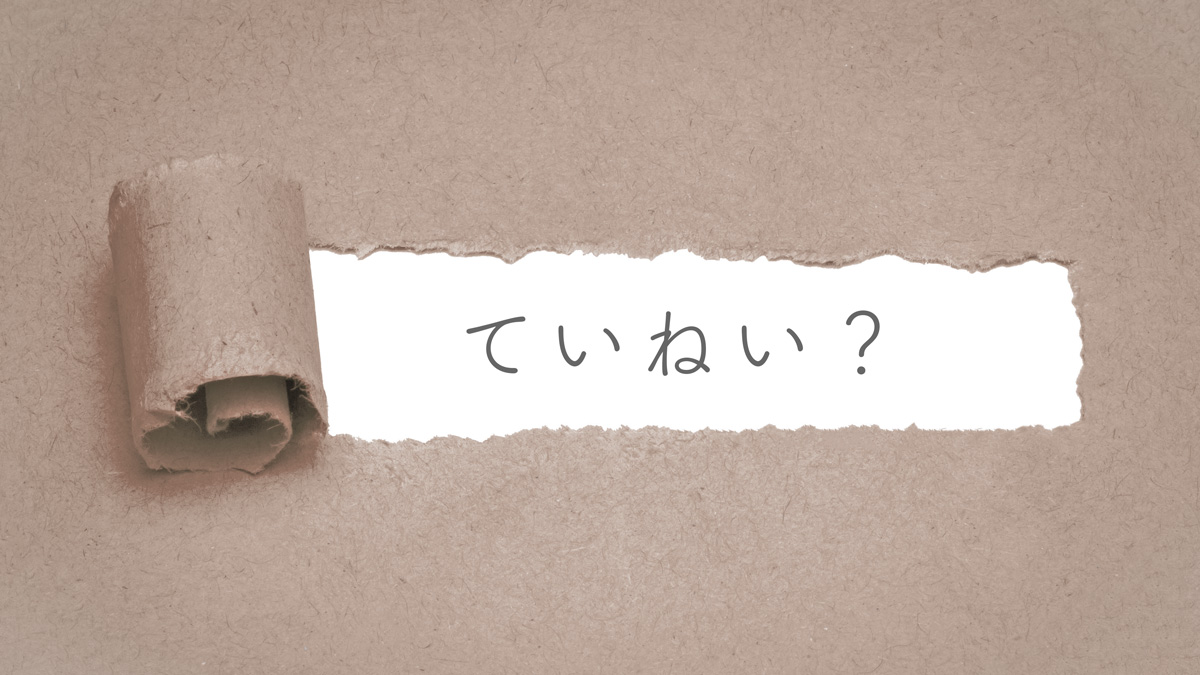
昨今のせわしないご時世からか、丁寧な暮らしや生き方を大事にしようという風潮も高まっている。「丁寧な〇〇」に憧れたりもする。それは、おそらく自分にとって非現実的だから。当たり前にできていることに憧れたりはしない。
でも、丁寧って憧れることなのだろうか。
たとえば、料理をお出汁から作るとか、掃除機ではなくこだわりの箒で掃くとか、植物を育てるとか、時間や手間を惜しまずなにかをするとか ──
「行為」そのものにフォーカスされがちだけれど、丁寧って、そもそも内側から自然と滲み出るようなもの。
意識せずともそうなってしまう心の状態なのではないか。
行為としての丁寧、姿勢としての丁寧
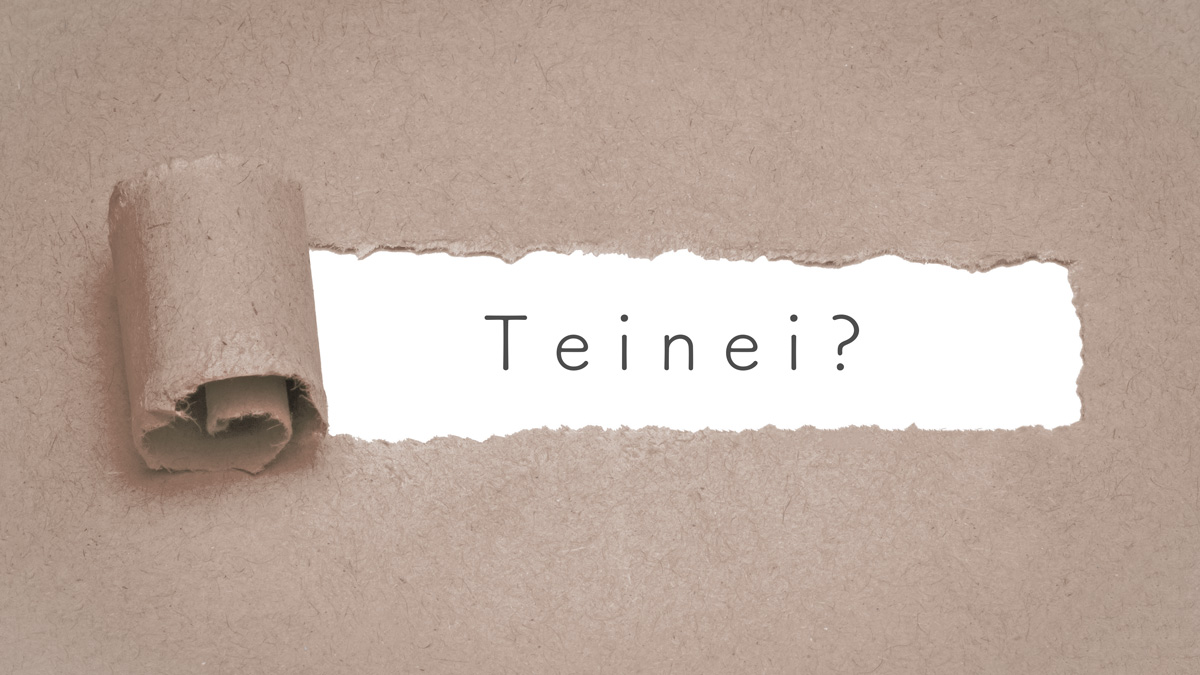
農産品や工芸品の世界では、「丁寧に丹精込めて作りました」という言葉がよく使われる。それは、工程の多さや手間の多さを示す言葉でもあり、「適当に作っていませんよ」という意思表示でもある。
丁寧は本来、行為ではないから目には見えにくい。
だから作り手は、あえて行為を可視化させて、その裏にある姿勢を感じとってもらおうとする。
姿勢 → 行為 → かたち。
でも、同じ「丁寧」でも、目的が変われば意味が変わる。個々の暮らしのなかの丁寧さは、誰かに示すためのものではなく、内側に向かれたもの。
行為はその結果にすぎない。
もちろん、丁寧とされる行為をしているうちに、姿勢が培われることもあるから、それを逆手にとって日常にしてしまうのもありだけど、丁寧の本質はやはり姿勢のほうにあると思う。
農業を通した、私の中の丁寧さ
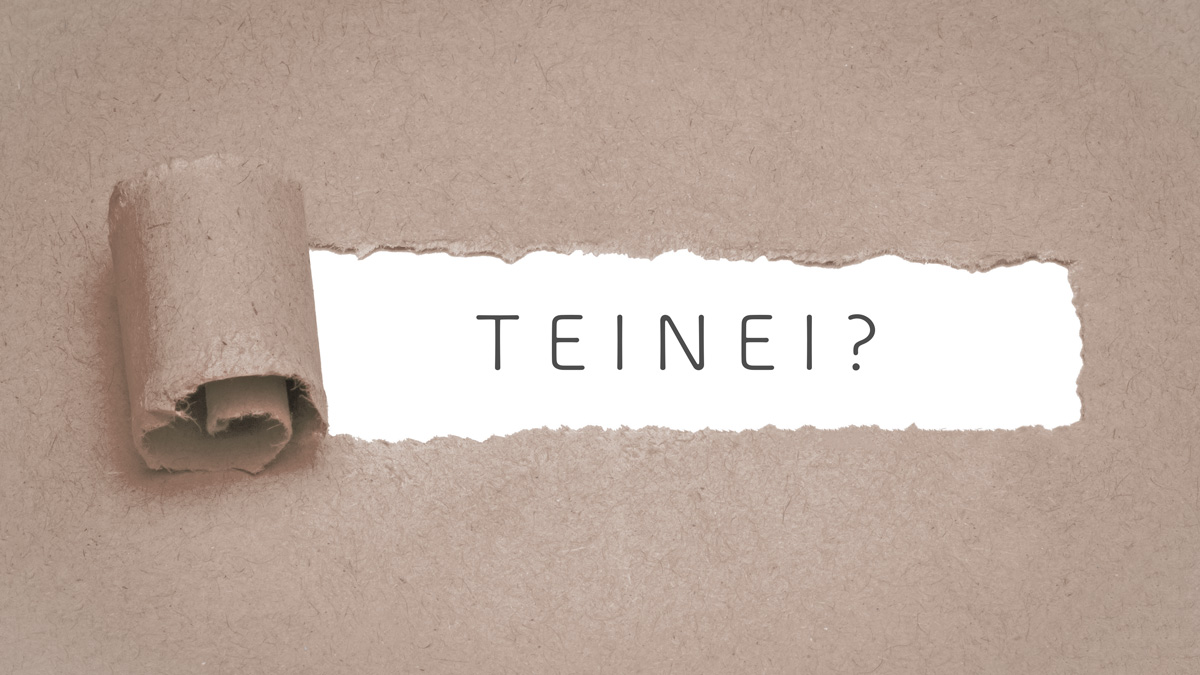
作業を他者に見られたり一緒にする機会があると、たいてい、丁寧だね、といわれる。雑にやっているわけではないからきっと丁寧なのだろうが、本人としてはそんな自覚は全くない。無意識にそうなってしまっている。
当初は、丈夫だから「適当でも育つ」と思って始めたさとうきび栽培だったけれど、気づけばあれやこれやと気にかけ、土寄せやライン引き、支柱の立て方、苗の保管の仕方など、側から見るとひとつひとつにバカがつくほど丁寧に取り組んでいたらしい。
そういわれてみると、確かにもっと雑な扱いでも十分なはずだったよな、と思いつつ──
やっぱりそうせずにはいられない。
わたしにとっては、それがあたりまえの心の在り方、デフォルトらしい。
作付面積が増えて管理機に頼ることが増えると、機械の圧倒的なはやさに助かりつつも、機械がゆえの粗の多さも気になって仕方がない。効率的だけれど、痒いところに手が届かないのだ。
手でなおせるところはなおすけれど、全部はさすがに無理。頭の中ではこれで良しとし、見て見ぬふりを決め込むものの、心の中はいつももやもやしている。
大規模栽培には向いていないのかもしれない。
丁寧は、誰のためか
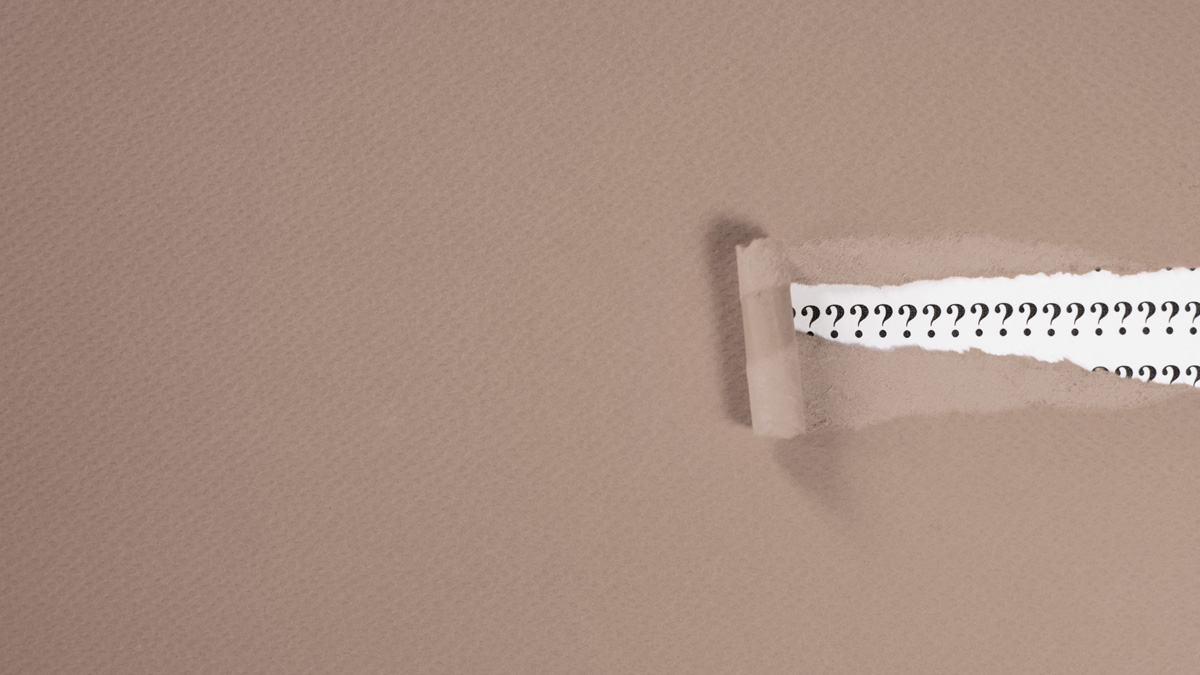
なぜそこまで丁寧にやる必要があるのか。
作物のためと思って取り組んでいた丁寧さは、本当に作物のためなのか、と改めて自問してみる。
もちろん作物のため、と言えるところも大いにあるけれど……。
ーー結局のところ、自分が心地よいからそうせずにはいられないだけなのかもしれない。一言で言えば、性分なのだと思う。
でも、自分が心地よくいるための丁寧さが、巡り巡って作物の心地よさや、加工品の仕上がりの良さにつながっているのなら、それはもう、結果的に「みんなのため」になっているのではないか。
丁寧の起点が、自分であっても良いと思いたい。
丁寧にもグラデーションがある
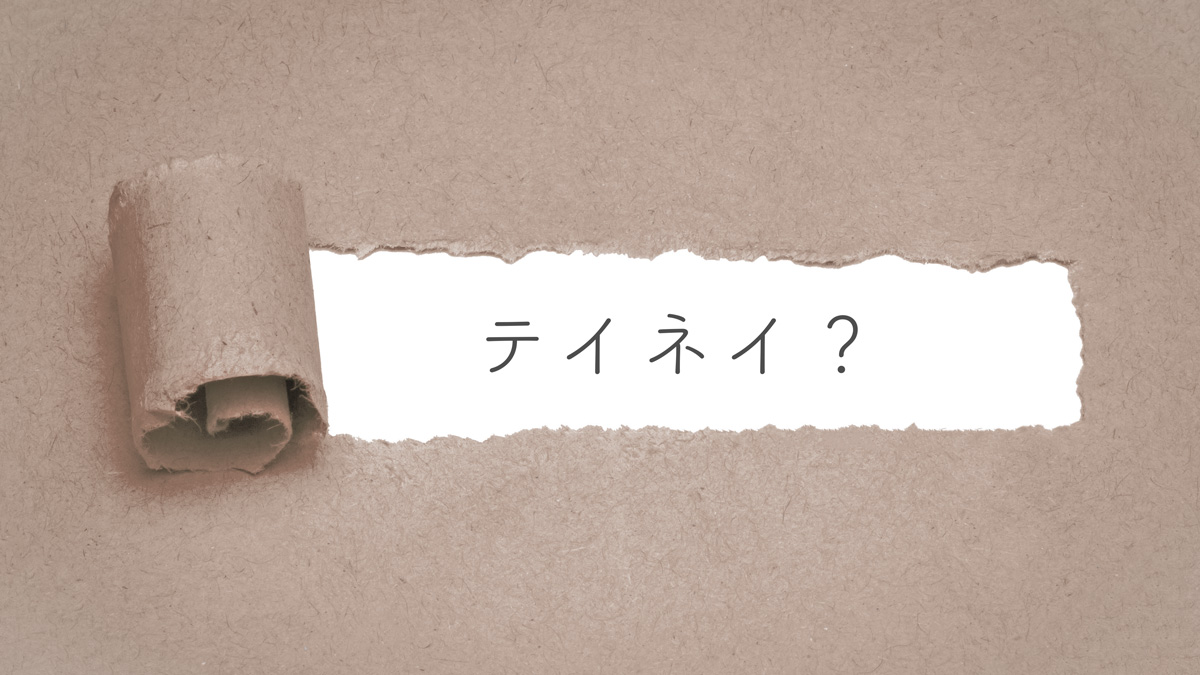
丁寧は、人によって加減も基準もまるで違う。
ある人にとっては十分丁寧でも、わたしから見ればそうとは感じないこともある。
逆に、わたしが丁寧にやったつもりでも、誰かにとっては過剰かもしれない。
どこを大切にしたいかが違えば、丁寧のかたちも変わる。だから、丁寧の程度に「正解」はない。
社会の秩序や企業内のルールとして、丁寧としての行為の基準が設けられていることに異論はないけれど、丁寧の正解を他者に押しつけてはならないと、いつも反省しているし、肝に銘じてもいる。
そして、こんな「丁寧気質」な性分の私でも、日常のすべてにおいて丁寧なわけではない。
気にするところと、まったく気にしないところがある。誰にも迷惑をかけない範囲なら、とことん手を抜く時だってある。
それでも、何かや誰かとの関わりが生まれた瞬間、自然と丁寧のスイッチが入ってしまう。
もしかすると、丁寧とは関係性に呼応して生まれる姿勢でもあるのかもしれない。
おわりに
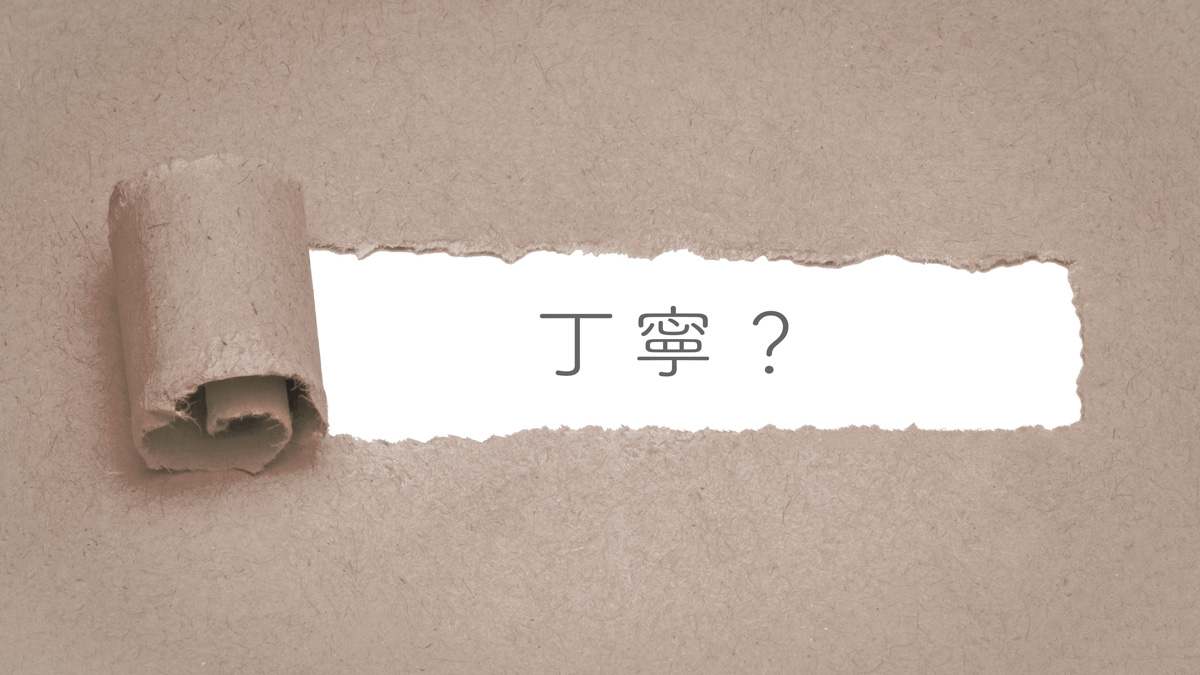
丁寧は本来、行為ではなく内側から滲み出る心のあり方、姿勢であり、行為はその表れ。
ちまたで「丁寧な暮らし」や「丁寧な生きかた」が、行為やスタイルとして語られがちなのは、単に「みため」としてわかりやすいからだと思う。本来はだれかに見せるためのパフォーマンスでも美化される行為でも、正しさの象徴でもないのかなと。
私の丁寧さに限っては、みためにカッコよくもなければ素敵でもなく、もっと不格好で不器用で抗えない心の状態。心地よくても、度が過ぎると時に自分の首を絞めて苦しくなったり、面倒に思ったり。
…そんな丁寧だってあるのだと、言っておきたい。