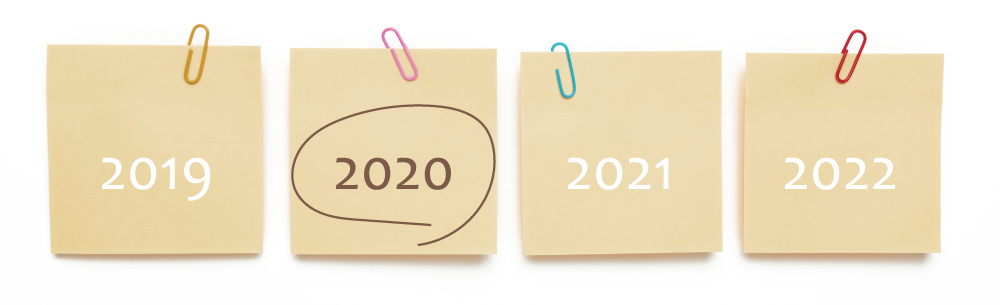
「とにかくまずはやってみよう」と一歩ずつ失敗と成功を繰り返しながらなんとかつづけたさとうきび栽培。
2020年12月。2年をかけてようやく黒糖をつくる準備が整いました。
どんな黒糖がつくれるだろう。そもそも、うまくつくれるのだろうか。
不安と期待の中、さとうきびを刈るため、夜明けとともに軽トラックでさとうきび畑に向かいました。
初冬の冷たい空っ風にあおられ、さとうきびは東になびきながらざわざわ波のように揺れ動いていました。
もったいないなと思いながらも、「いままでありがとう」とひと声かけ、一本一本丁寧に刈り取っていきます。
細かったり、太かったり、大きかったり、小さかったり。ふぞろいながらも頑張って育ってくれたことをとても誇らしく感じながら。
とりあえず100本ほどカットしたさとうきび。葉っぱも一枚一枚専用の鎌で剥き、キレイに洗ったあとで小さな製糖所へと移動。
搾汁機の出番にワクワクしながら、ローラーの入り口にさとうきびの茎をいれて搾ってみました。
小さいながらもパワフルな搾汁機。
さとうきびの茎は悲しいくらい見事にぺったんこになり、同時にたくさんのジュースが蛇口から出てきました。
さとうきびのジュースは、透き通ったキレイな緑茶色。ひと口飲んでみるとスイカのようなほのかで心地よい甘さが広がりました。
搾ったジュースは、酸化しないうちに早速火にかけます。
何時間も丁寧にアクを取り続けながら、まだかまだかと待ちわびつつ煮詰めていくと、次第にメープルシロップのような色味に変わり、製糖所が甘く芳醇な香りに包まれ始めました。
あー、なんて幸せな香り。
その後も焦げつかないよう時折かき混ぜながら、さらに煮詰めていきます。
シロップは110度を超えたあたりからぐんぐん温度が上がっていきます。あともう少し。
キャラメルとはまた違う、さとうきびならではの複合的な香りがより一層増していきます。
焦げ付かないよう慎重に撹拌を続け、いよいよ目標の温度に達したところで直ちに火を止め、今度はゆっくりと冷ましていきます。
すると、急に様子が変わり始めました。
あわててバットに移すとみるみる固まっていき、ほやほやの黒糖が、ついに姿を現したのです。

思ったよりずいぶんと琥珀色!
美しく固まった琥珀色の黒糖をしばし眺めたのち、まだほんのりと温かいそれを、そっと手にとり口に含んでみました。
あれっ?
一瞬、思考が停止したのを感じました。
その風味をようやくカラダがキャッチしたとき、思考がゆっくりと戻ってきました。
思っていたのと違う。
…さとうきびって、こんな風味だったの?
その風味は、期待はずれどころか、想像を超える豊かで味わい深い甘味でした。温かいから余計に。
酸味も後追いでほのかに感じます。
もう、いままで知っていた黒糖とは、全くの別ものでした。
初めて口にした、さとうきび本来の天然の甘味。じんわり、ゆっくりカラダに沁み渡ったとき、「カラダが喜ぶ」という感覚を、確かに感じました。
採れたての野菜をまるかじりして衝撃を受けたとか、まさに運命の出会いだったとか、たまにききます。
そんなことって本当にあるのかなぁ、と内心思っていました。
今回の初製糖で、そういった感覚が自分の身にも起こることを少しは期待もしたけれど、そうはいっても黒糖は黒糖。どんな風味かは既に知っていたので、衝撃とか雷が落ちるとかそんな体験はきっと訪れることはないだろうと、わりと冷静でいました。
それよりも、黒糖がうまくつくれたら、なにかと合わせてコーヒーとかお菓子とかに活用できたらいいな、何と合うだろうかと脇役で使うことばかりを色々考えていたくらいです。
そんな心づもりでいたのに、図らずも初めてつくった黒糖で、心が揺さぶられる体験をしてしまったのだから、まさにうれしい誤算でした。
さとうきびに大いなる可能性を感じたあの瞬間から、さらに2年。
今思えば、初めてつくった黒糖は、はじめてにして最高傑作の風味と出来栄えでした。いまでもあのときの風味は忘れることができません。
あの風味を追い求めながら、黒糖の枠にとらわれない、新しいさとうきびのカタチを開発する過程で、ここには書ききれないほど想定外の苦しみに直面しました。
さとうきびが持つ性質の不安定さが、自分たちが目指すお砂糖のカタチに仕上げるうえでの大きな障壁となり、心折れる日々。
毎回異なる仕上がりをまえに、さとうきびという自然に生きるものと関わることは、安定とコントロールを手放すことだと突きつけられたのです。
でも、どんなにうまくいかないことがあっても、自然のまえに打ちのめされても、いつでも、どんな環境でもそこで懸命に生きるさとうきびをみていると、不思議とまた頑張ろうと思えてくるのです。
さとうきびの魅力を伝えたいという自分の中で変わらない想いがあるかぎり、そこにさとうきびが存在する限り、きっと離れることなんてできないだろうな。
そう思って、今日もさとうきびに寄り添っています。