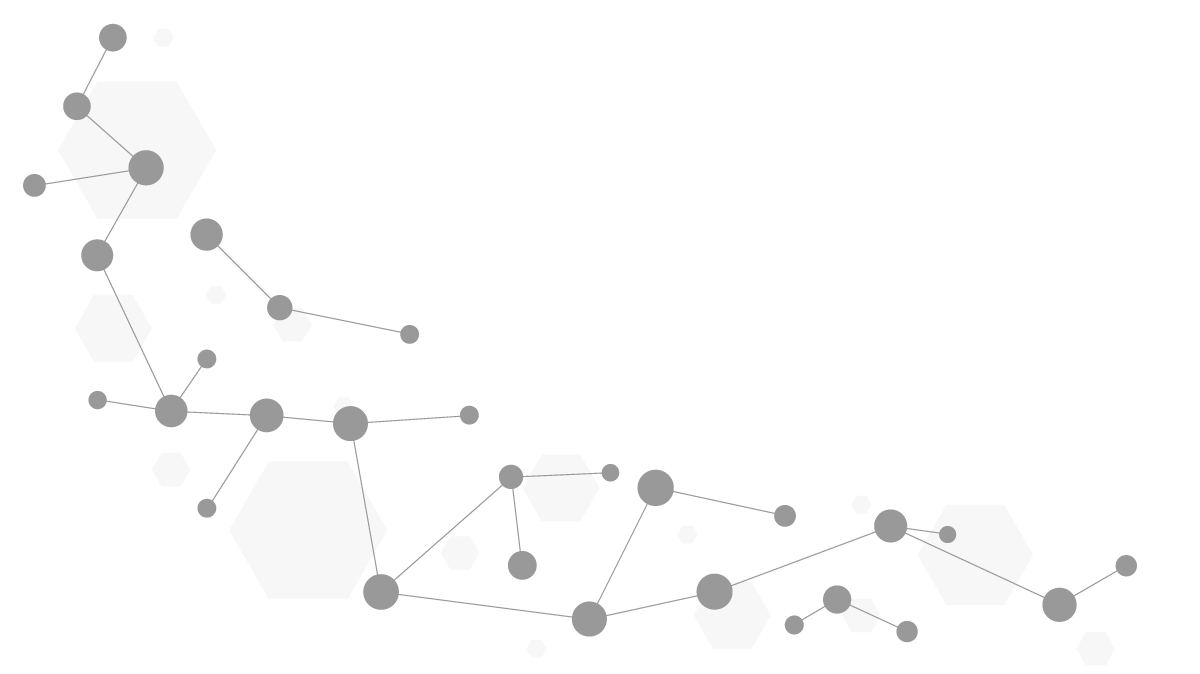
今日は3月10日、お砂糖の日です。
さとうきびを育み、初めて加工して含蜜糖をつくってみてから早5年。
今回は、加工を続ける中で、散らばっていたひとつひとつの事象が、5年目にしてようやく一本の線でつながり、理想の「さとうきびクリーム」に向けて大きく一歩前進した、そんなお話です。
初年度に試作をしたときは偶然と幸運が重なってすばらしい出来栄えだった含蜜糖も、年を重ねるごとに、その繊細さを痛感するようになりました。
搾汁液をそのまま煮詰めて作る「さとうきびシロップ」を、もっと高温で煮詰めて結晶化させる含蜜糖作り(黒糖も)は、みなさんが思っている以上に奥が深いです。
結晶化という現象は、ショ糖以外の不純物をたくさん含めば含むほど難しくなるからです。
それなのにわたしたちは、不純物を除去する石灰を使わず、さらには完全に結晶化させて固まらせる固形よりももっと不安定な、半固形のカタチを商品化することにしました。それは、どこにも製法のこたえが載っていない、まさに未知の領域でした。
まだ十分に積み上がっていない経験を積み上げるべく、参考になりそうな文献をしらみつぶしにあたり、ひたすらに試行錯誤を繰り返して結晶化と向き合ってきました。
最終的には勘どころも大事な要素ですが、勘は勘でも、確かな経験値からくる勘でなければ意味がありません。
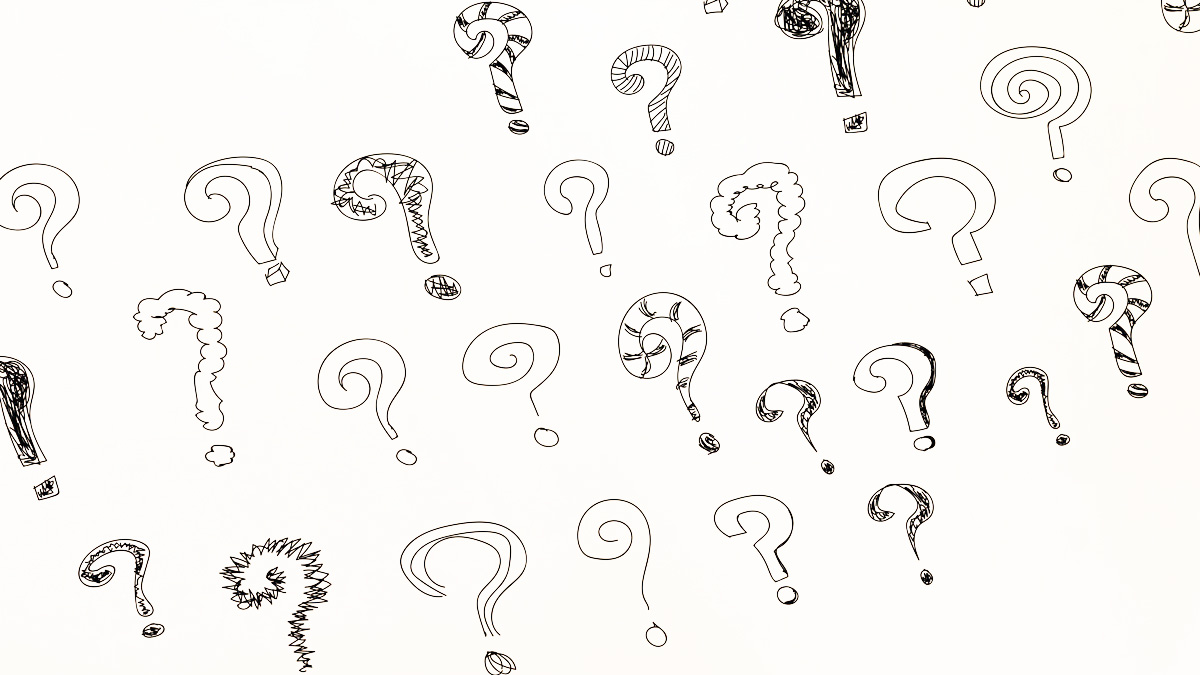
月日は経ち、商品はなんとか完成させましたが、それでもなお、いくつか説明のつかない事象がありました。確かな事実として目の前に現れてはいるけれど、なぜそうなったのかがわからない。仮説を立てても確信には至らず、事象は点となって散らばり、宙に浮いたままでした。
栽培から検証するにしても、さとうきびは、一年に一回しか収穫できません。とにかく時間がかかります。
しばらくは、もうそんなものだろうとわからないまま受け入れつつありました。むしろ個体差があって然るべきさとうきびを前に、すべてをわかろうとするなんて驕りだと自分にいいきかせてさえいました。
でも、
もやもやした状態は変わらず、業務に追われながらも心のどこかでずっとひっかかっていました。これからもずっと確信が持てないまま、なんとなくでやっていくのかと。
・・・・・・・・
そんな思いを払拭すべく、この機にもう一度、徹底的に検証してみることにしました。改めて立てた、ある仮説をもとに。
内容に関しては、専門的な話になってしまうので簡単に説明すると、どんな環境や状態で育ったさとうきびが、どんな仕上がりになる傾向にあるのか、この因果関係をよりあきらかにするための実験です。
また、半固形の結晶化したカタチになる直前のある変化に着目し、この状態がどんな条件のときに変化し始めるのか、より正確に捉えるための実験も兼ねていました。
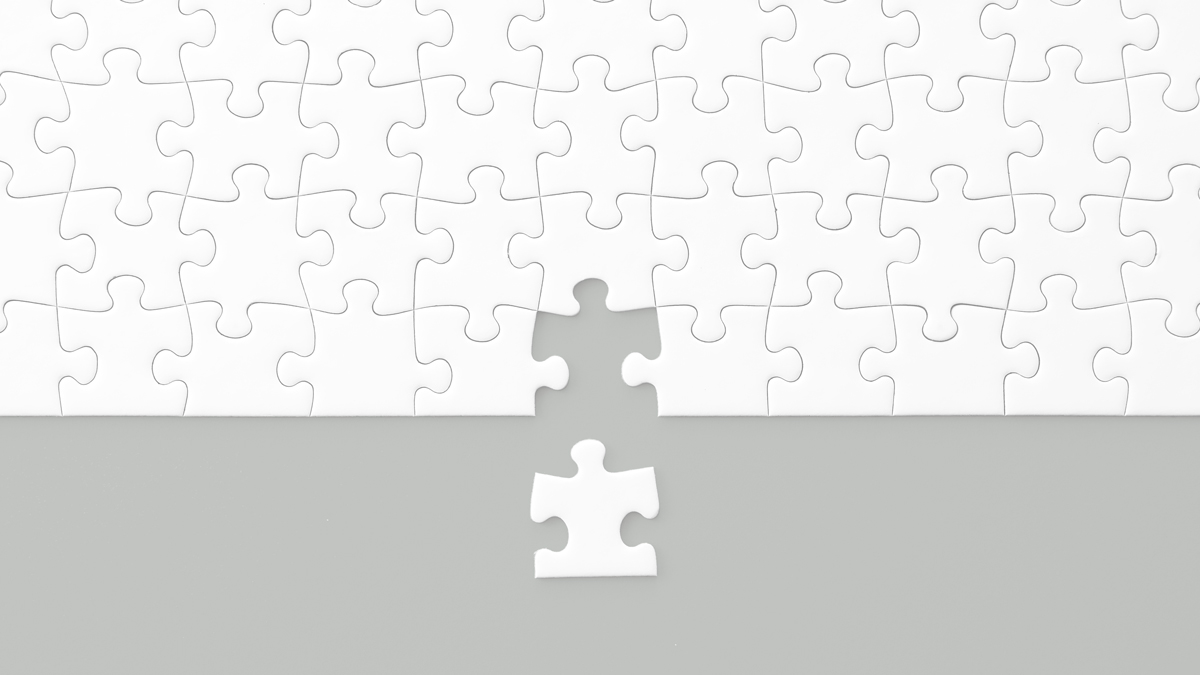
検証のための実験は十数回にわたり、失敗を交えながらも思っていたよりは順調に進みました。勘ではなく、これまでの経験からくる読みが結果にしっかり反映されているーー今回はそんな手応えすら、不思議と感じていました。
そして、いよいよ核心へと迫る最後の実験。ついに、最後のピースがぴたりとはまったのです。
「こうだったらこうなるはず」—— この仮説が、ここにきてようやく立証されました。
あらためて過去のデータを洗いざらい見返してみると、別々の時期に何気なく記録していたとりとめのない事象が、実はすべて関連し合っていたことにも気づきました。
「だから、こんなことやあんなことが起きていたのか!」
それは、散らばっていた点と点が、まさに一つの線でつながった瞬間でもありました。

さとうきびが育つ環境―育みかた―加工の方法。つながっていることは何となく想像はついても、具体的に何がどうして、どこにどうつながっているのか、確信を持って気づけたのは、数多くの失敗と熟考を重ね続けてきたからこそ。
続けてこなければ決して辿り着けなかった気づきでした。
また、今回の発見は、コントロールが難しいと思っていた風味や質感の再現性を高める大きな一歩ともなりました。
実は、理想とする風味を100%再現できなかった時期があり、それに対しても原因がはっきりせずにずっとひっかかっていたのです。
もちろんどの年のさとうきびにもそれぞれの良さがあります。風味も絶対的な正解はありません。でも、できることなら初めてつくったときに感じた、あの風味を味わってもらいたいという想いがすべての原動力になっています。だからこそ、どうしても解決したい課題でした。
これで大きな霧は晴れましたが、ゴールではありません。不明な点や課題はまだたくさんあります。
それに今回、点と点がつながったことで、わたしたちの目指す風味を作り出すには、多くの制約があることもわかりました。
今後の育み方も見直す必要があるし、引き続き実験を重ねて毎年検証していかなければなりません。
今年度も改良と改善を重ねながら、より良い商品をお届けできるよう邁進してまいります。
今までご購入くださったかたも、これからご縁のあるかたも、どうか温かく応援していただけたら嬉しいです。
それにしても、何がどうつながっているのかは、その時には意外とわからないもの。でも、今回のようにわからなくても続けたその先に、思いがけずふとつながる瞬間が待っているのかもしれません。
だから、自然とつながる日が来るまで、ただ粛々と続けていけばいい。そんなふうに実感できたのも大きな収穫でした。