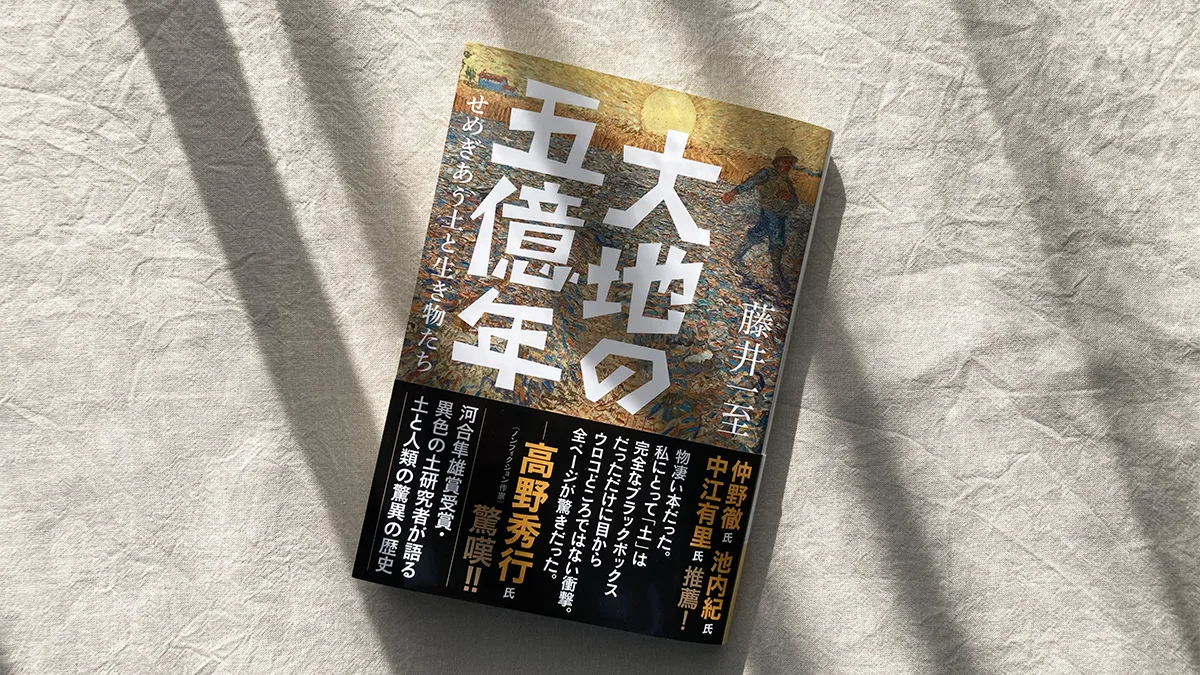
幼い頃、校庭の土で「コンコン集め」をして遊んだ記憶があります。表面のざらついた砂を避け、その下にわずかにあるきなこのように細かい土だけを手でかき集める。どれだけ細かい土を集めることができるか夢中でした。泥遊びもたくさんしました。あの頃は、土がなんなのかなんて全く理解していませんでしたが、確かに身近な存在でした。
次第に土と遊ぶこともなくなり、距離ができ…。
そして今、数十年の時を経てさとうきび農家となり、再び土と触れ合う日々の中で手に取ったのが、土の研究者、藤井一至さんの著書『大地の五億年 せめぎあう土と生き物たち』でした。
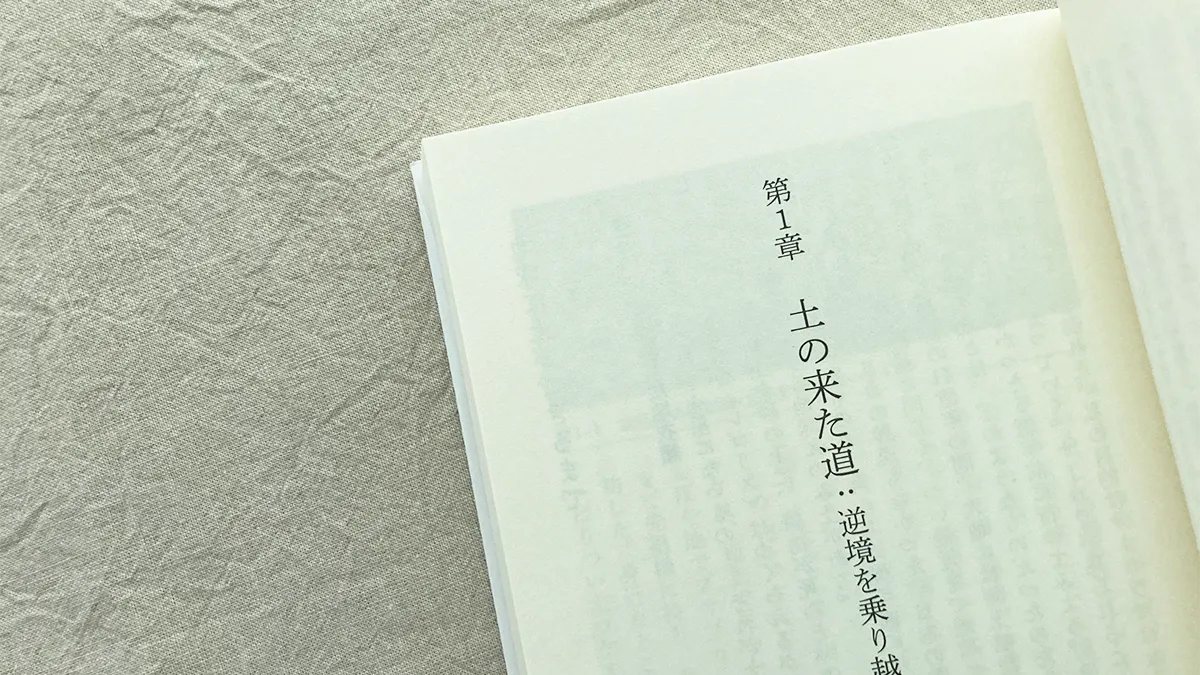
第1章では、土が誕生した5億年前まで遡り、聞いたこともないカタカナや専門用語をはさみながらどのように土が形成されていったのか、丁寧に綴られています。
気の遠くなるほどの長い軌跡と奇跡。
じっくり、ねっとり、静寂のなか積み重ねられてきたその時間を思うと、なんともいえない感慨深さがありました。
地球最初の土はイエローナイフにあり、地衣類や苔の遺骸(有機物)、砂や粘土が混ざり合ったものだったこと。
そこからさらに一億年!かけて水辺に砂や粘土を堆積。4億年前に新たにシダ植物が現れたことで泥炭土(植物遺体が水の中で分解されずに堆積した土壌)が形成され、これが石炭のもととなったこと。
やがて3億年前になると、シダ植物の代わりに樹木などの裸子植物が主役となり、森が形成され、落ち葉や倒木による有機物が陸上に堆積。微生物が分解しにくいリグニンという物質のせいで分解が進まず、堆積の一途を辿るかと思いきや、リグニンを分解する能力をついに獲得した白色腐朽菌(菌糸)が増加したおかげで、自然の循環が始まったこと。(ちなみに菌糸の一部が子実体となったのが、あのおなじみのキノコです。)

いま、こうしてあたりまえのように営まれている自然の循環は、なんと樹木と菌糸のおかげだったのです。
そういえば、リグニンを含むさとうきびの残渣を一部土にすき込んでいる箇所は、秋雨が続くとキノコが生えます。菌糸の種類は違うかもしれませんが、同じように分解に貢献してくれているのだから、キノコさまさまです。
第2章は、土を取り巻く動物たちにフォーカスし、さらなる土の発達に貢献しているさまざまな動物を交えながら話が進みます。
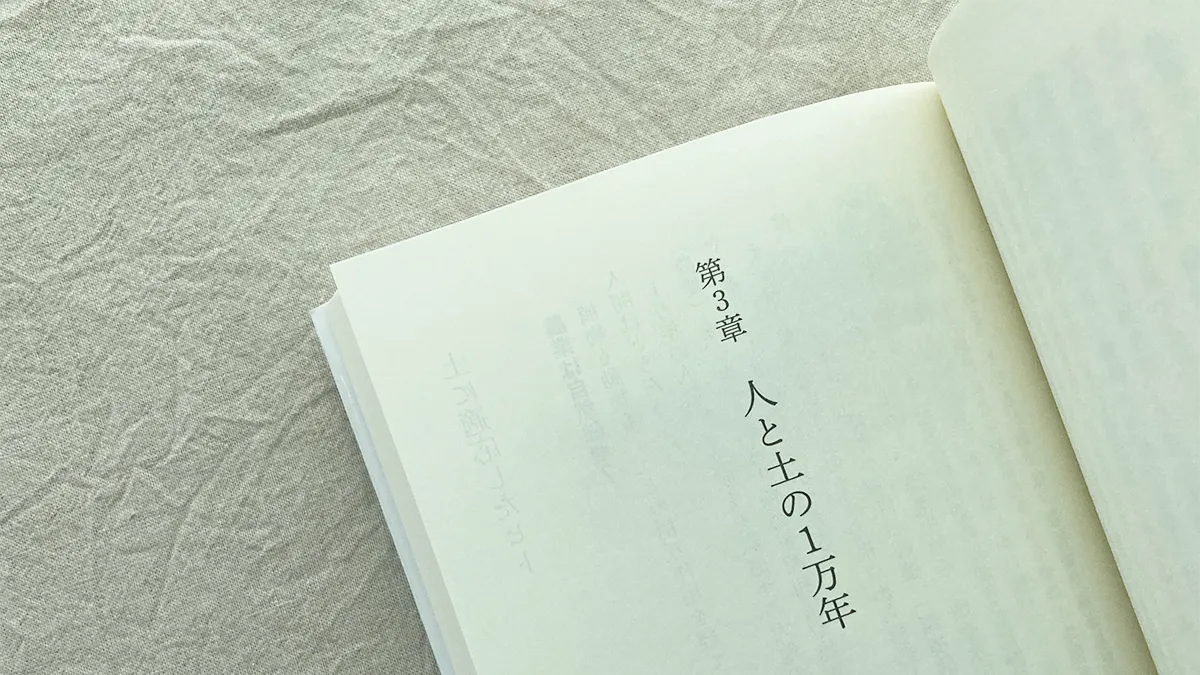
そして第3章。ようやく人と土との関係、農業の話にたどり着きます。
5億年の土の歴史に対し、人が土で作物を育て始めたのは1万年前。まだまだ土の歴史の中では浅いのですね。先人たちが、食料を確保するための試行錯誤は、現代の農業とも重なり、一気に身近に感じられました。
なかでも、環境や土の性質を活かした稲作の話は知らないことも多く、へぇ!の連続。
たとえば、
世界の低地面積全体の30パーセント近くがアジアの熱帯地域に集中しているが、それは、メコン川(タイ)、長江(中国)、ガンジス川(バングラデシュ)といった大河の賜物である。この地の利を生かして広まったのが水田稲作だ。イネは、作付面積こそ世界の耕作面積の10パーセント足らずだが、世界人口70億人のうち半分近くの主食となっている。
第3章p191-192
稲作、お米、本当に有難いです。

一方、大河がなくとも、四方を海に囲まれ、3000メートル級の山脈がそびえ、活火山も多い日本。
山から海へと滝のように流れる豊富な水が川となり、大地を削り、時に災害を引き起こしながら、水田に適した土地がつくられてきたおかげで、稲作を長く支えてきたという…。
まさに日本の地形の賜物です。
翻っていまは、せっかくの田んぼが宅地や耕作放棄地へと姿を変え、米離れ、担い手不足、価格の変動…さまざまな問題に直面しています。田んぼは使われなければすぐに荒れ、どこからともなく運ばれた土によって重機であっという間に埋められ、消えてしまいます。
ほんの一瞬で、受け継がれてきた営みが断ち切られるのです。
農家だけど、お米をつくっているわけでもないわたしが、お米や田んぼのことを憂う資格があるのかはわかりません。ただ眺めているだけの自分が、宅地化を惜しむのは勝手な感傷かもしれません。
それでも、ほんの数十年まえまでの、田んぼや畑に囲まれで育ったあの頃の当たり前の風景が、実際に消えてなくなっている現実を思うと、どうしたって胸の奥がざわついてしまいます。

また、かつての日本の農業は100%有機でしたが、肥料資源が足りずにやみくもに山を削り、草山やはげ山が広がった歴史があったことも知りました。
昔の農の姿が100%理想というわけではなかったのです。
全て自然にあるもので作物の肥やしにするには限界があった。さまざまな失敗と積み重ねの中で今の姿があり、そしていまもなお試行錯誤が続いている。
現代農業は批判されがちですが、土と人との関係は長い土の歴史でいったらまだまだ始まったばかり。良いところも悪いところも含め、より良い未来へと向かう過程の真っ只中にいるのだと気づかされます。
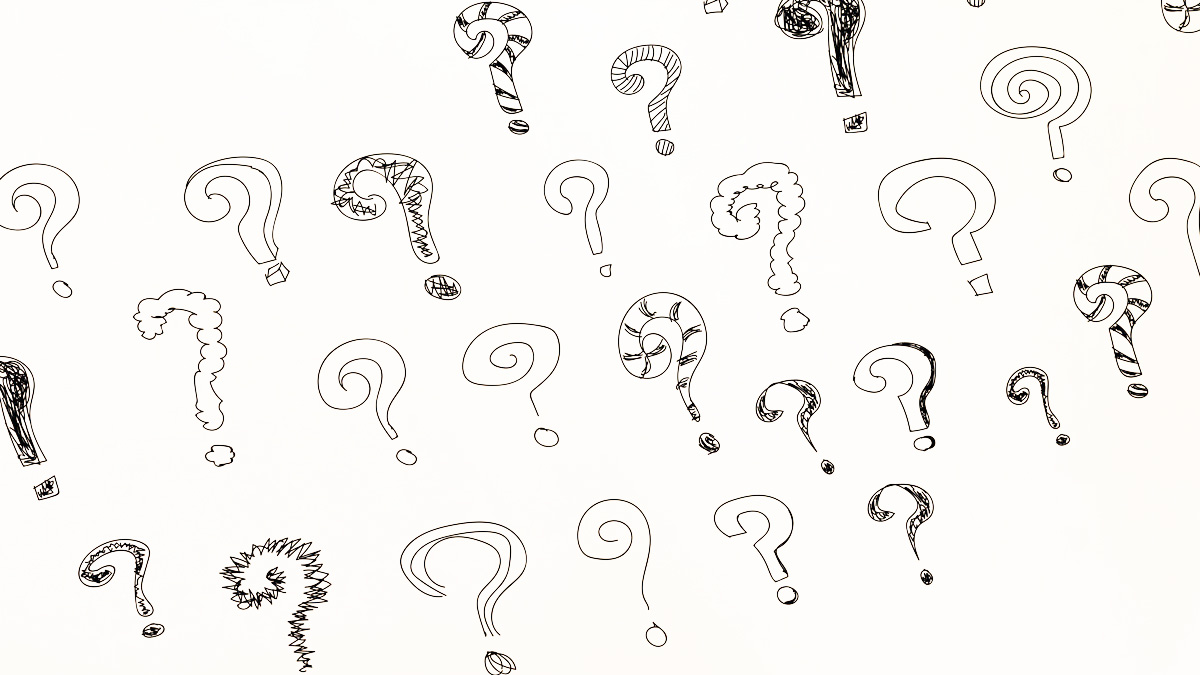
あらためて、土とはなんなのか。
それは、岩石の風化によって生まれた砂や粘土に動植物遺体が混ざったもの。砂や粘土だけでは土とはいえないのです。
岩石だけが風化しても、植物や動物が存在しなければ、土も存在し得なかったし、土がなければ、文明も文化も今の豊かさも育まれることはなかった。
わたしたちの食卓を支えるほぼすべての作物は、この奇跡の土のおかげで育っている。あまりに尊い存在です。
・・・
ところで、土は世界では大きく12種類に分類されるそうです。
そのうちのひとつ、黒ぼく土という貴重な火山灰土は日本特有の土だそうです。わたしが農業を営む浜松市の地域には、富士山などの活火山が届かないところなので黒ぼく土はありません。
その代わりに、東に天竜川、西に浜名湖、南に遠州灘、北には山々と、自然に恵まれた土地です。場所によってさまざまな種類の土が採取でき、土質も色も大きく異なります。

わたしが管理している2つの畑はどちらも砂壌土ですが、粒子の大きさや構成比がわずかに違うだけで、さとうきびの育ち方や加工したときの風味はまったく異なります。土質って思っている以上に作物にものすごく影響をあたえるのです。
あとは水源との位置関係による水位の高低なども含め、土と水で作物の出来が9割がた決まる現実。人の手で補える部分もありますが、風味まではそう簡単に変えられません。
その作物にあった土質で育てることが、おいしさに直結する。だからこそ産地が生まれるのだと深く納得しています。
まだまだ謎が多く、解明されていないことが山ほどある土を、本書では、「宇宙」と比喩されています。
土中に存在する微生物は何百億個。小さな生き物も多数。目に見えない世界がわずか1mあまりの地層に広がっています。人が簡単にコントロールできない聖域ともいえます。「土を整える」という言葉さえ、少しおこがましく感じるほどです。
一方で、そんな土を前に、日々の畑では草と格闘している自分がいます。5億年の重みより、なんでこうもまあ雑草が次から次へと、と目の前の現実にうんざりする日々。土の偉大さも、神秘さも、雑草で一気に現実に引き戻されるのだから、滑稽です。
でもこの本が、土への感謝をもう一度思い出させてくれるきっかけを与えてくれました。憎らしい雑草でさえ、むき出しの土を守る役割があり、それもまた、必然なのだと。

山や森、公園や神社、畑や田んぼだけでなく、アスファルトや建物の下にも、土が広がっています。農業に関わらなくたって、誰の身近にもある土。
けれど、決してあたりまえにそこにあるわけじゃない。
『大地の五億年』は、そんな気づきを与えてくれる一冊です。あなたも、足元の宇宙に思いを馳せてみませんか。